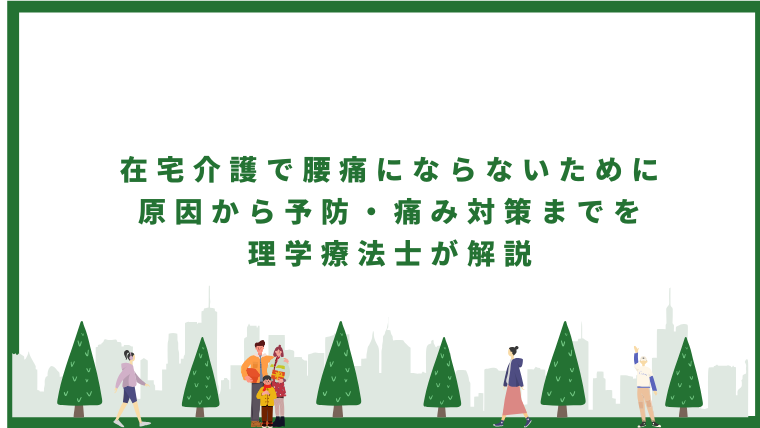トイレ介助で腰を痛めないための動き方|体を守るコツとおすすめアイテム
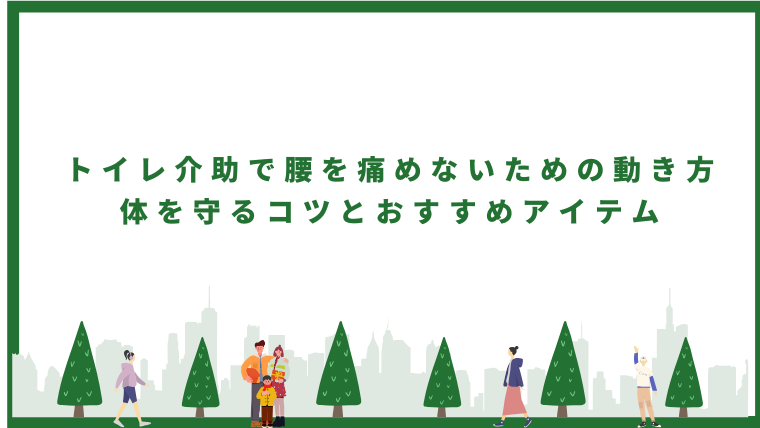
はじめに|介助する人の「体を守る」大切さ
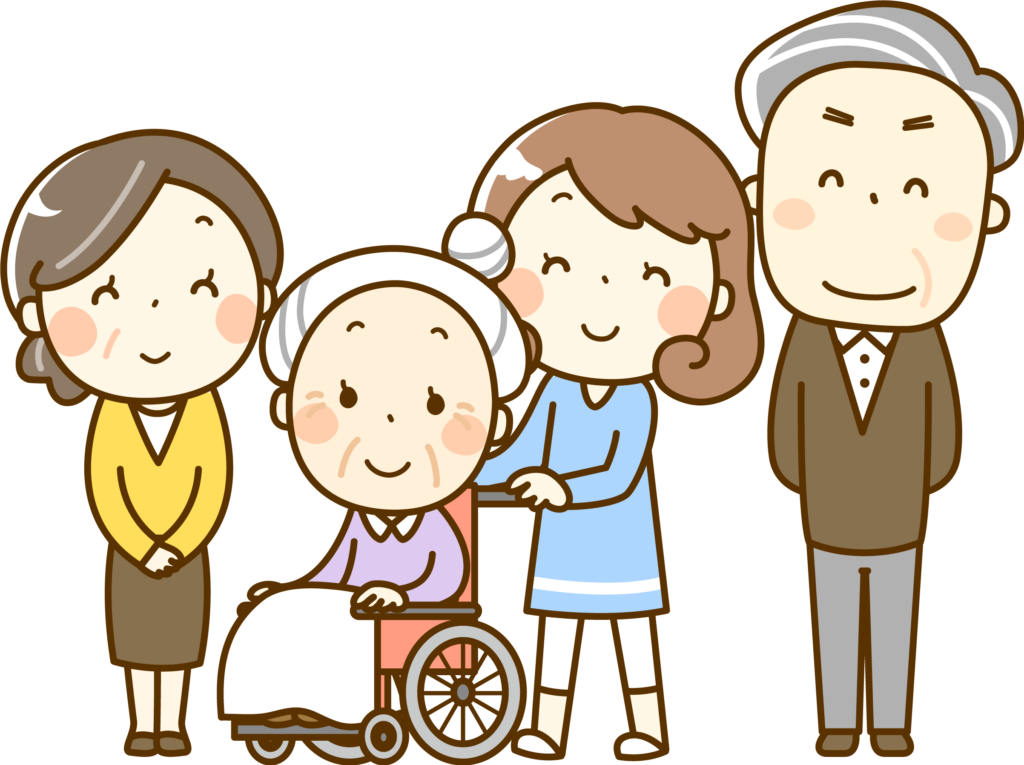
「お母さん、トイレ行きたいって…」
日常の介護の中で、トイレ介助は避けられない大切なケアです
しかし、何気ないこの動作が、介助する家族の腰に大きな負担をかけていることも事実です
訪問の現場では、ぎっくり腰や慢性的な腰痛を訴えるご家族が多く、介助そのものがつらくなってしまうケースも少なくありません
そこでこの記事では、訪問看護ステーション勤務の理学療法士だから知っている「トイレ介助で腰を痛めないための体の使い方や、便利なアイテム」をご紹介します
ご自宅での介護を少しでもラクに、そして安全に行えるように、ぜひ最後まで読んでみてください
1. トイレ介助で腰を痛めやすい理由とは?
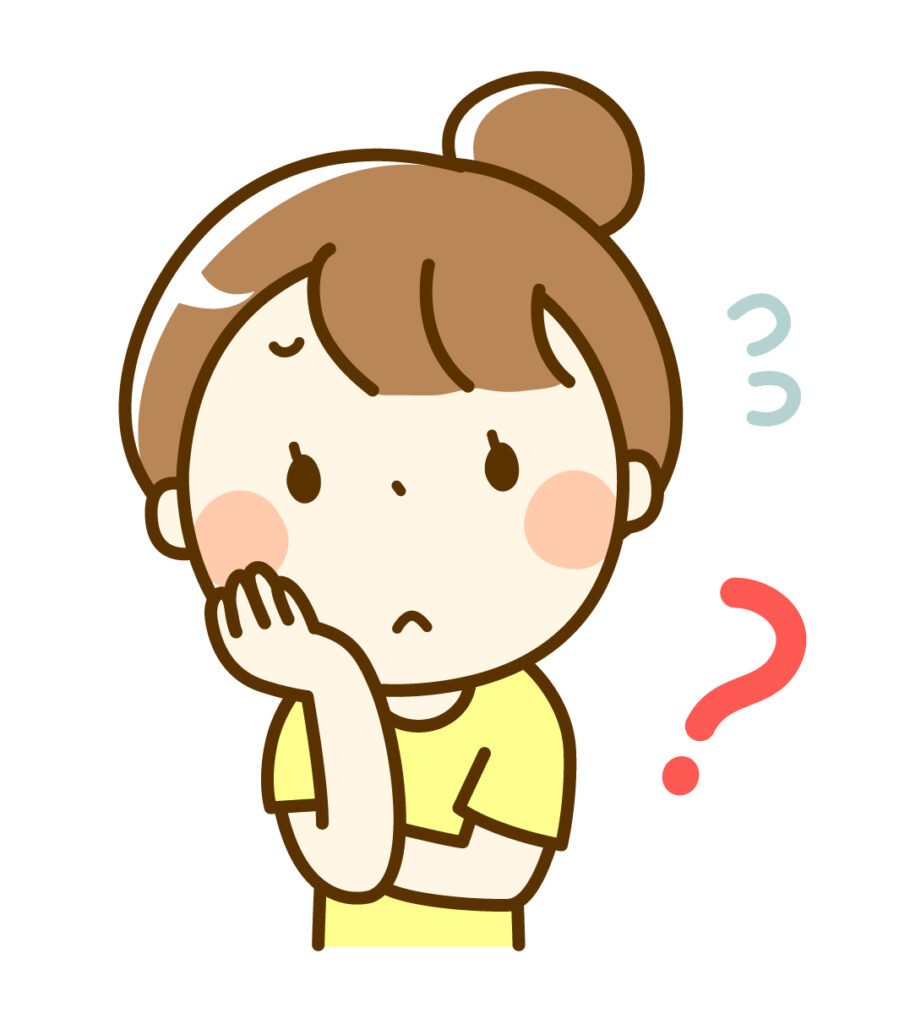
トイレ介助では、以下のような動作が頻繁に求められます
- 利用者を立たせる(立ち上がり介助)
- 向きを変える(方向転換)
- ズボンの上げ下ろし
- 便座への移動や座らせる動作
- 拭き取りなどの手元作業
これらの動作は、中腰・前かがみ・ねじりといった腰に大きな負担がかかる姿勢が多く、知らず知らずのうちに筋肉や関節にダメージが蓄積されていきます
2. 介助時の「基本姿勢」と体の使い方
腰を守るための3つのポイント
- 腰ではなく「脚」を使う
前かがみになるのではなく、膝と股関節を使ってしゃがむのが基本
スクワットのような動きが理想です - 重心を低く、利用者と「近づく」
腕を伸ばしての介助は腰に負担
しっかり近づいて、安定した重心を意識しましょう - ねじらない
腰をひねらず、足ごと方向を変える「ステップ動作」を意識しましょう
3. 実践編:動きを分解して解説
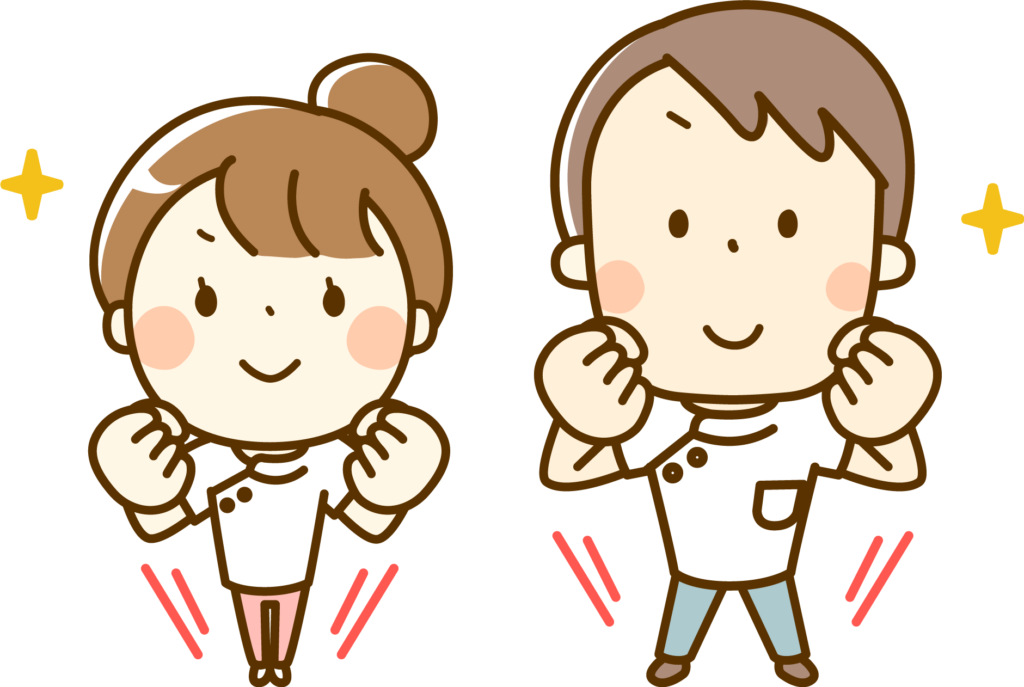
【ステップ1】立ち上がり介助
- 足は肩幅に
- 介助者は正面から近づき、腰を支える
- 「せーの」で前方へ一緒に動く
立ち上がりは上ではなく一度前に重心を移動してから、上に上がります
ポイント: 利用者を上へ引き上げるのではなく、「一緒に動く」イメージで
【ステップ2】移動・方向転換
- 無理に持ち上げない
- 利用者と一緒に足で方向転換
- 腰ではなく足を回転させる
ポイント:動くときは「右足から動くよ1.2.1.2」といった声掛けをするとお互いに動きやすいです
【ステップ3】座るとき
- 前傾姿勢を促す
- タイミングよく支えて“ドスン”とならないように
ポイント:立ち上がりの介助と同じように腰を曲げて腰で支えるのではなく、しっかり足で支えるようにしましょう
4. 腰痛予防に役立つおすすめアイテム
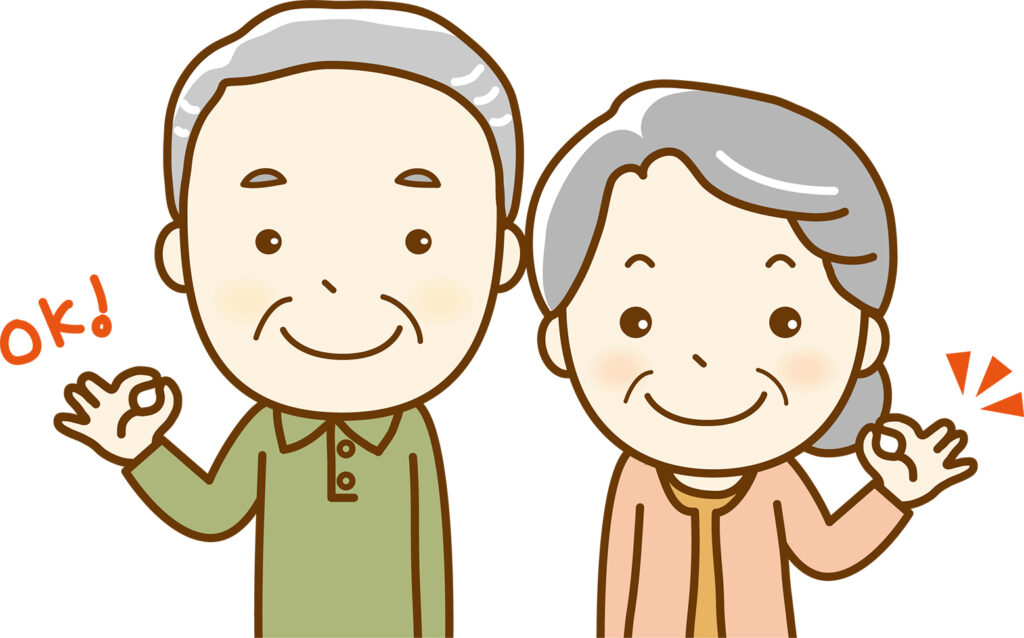
● 移乗用ベルト(スライディングベルト)
よくズボンを持って介助をする人が多いですが、ズボンが破れてしまったり足の付け根にズボンが食い込んで痛みが出やすいためあまりオススメできません
介助ベルトを使うと力の伝わり方が効率よくなり、介助者の負担が減ります
ズボンを下ろした状態でも使用できるのでトイレ介助で重宝します
● 腰サポーター(コルセット)
腰サポーターは介助するときの腰の負担を軽減してくれますが、商品によって効果はさまざまです
この商品は巻いてワイヤーを引くだけなのですが、サポート力が強くて紹介した利用者さん家族からも喜ばれました
もちろん予防的に使用するのも効果的です
● ポータブルトイレ(福祉用具)
毎回トイレまで連れていくのはちょっと…と思っている方は夜間だけポータブルトイレですることをおすすめします
移動の手間がなくなるだけでもかなり負担は軽減します
夜間のトイレに不安があるならコチラの記事がおすすめ
→夜間のトイレ、どう対策すればいい?訪問リハの視点から解説
5. 自宅のトイレ環境を見直そう
- トイレの出入口の広さ
- 介助スペース
- 手すりの位置
- 段差や滑りやすさ
福祉住環境コーディネーターやケアマネジャーに相談もできます
6. 介護保険で使えるサービスと福祉用具
- 住宅改修:最大20万円まで支給(1~3割負担)
- 福祉用具貸与/購入:移乗用ベルトやポータブルトイレなど
7. 家族の体も大切に|理学療法士からのアドバイス
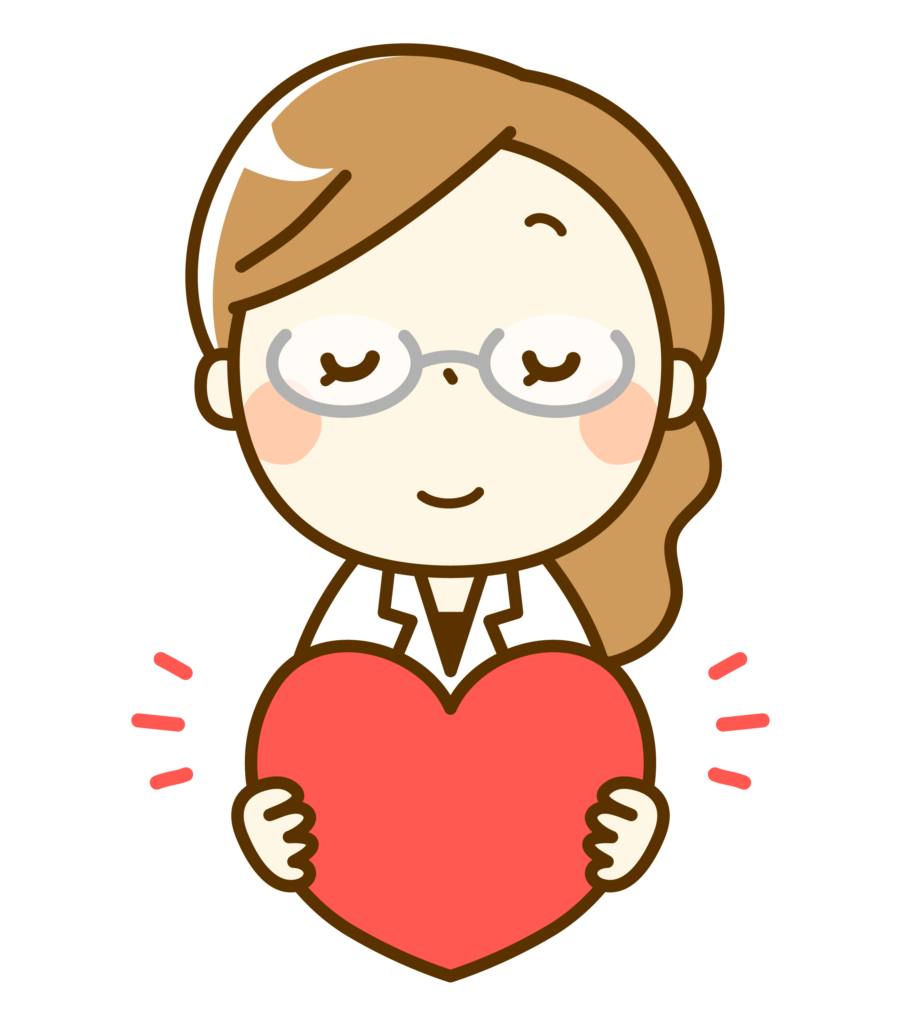
介助する人の体が壊れてしまっては本末転倒です
少しずつ「道具を使う・丁寧に動く」を意識しながら、無理のない介護を心がけましょう
8. まとめ
トイレ介助をラクに・安全に行うためのポイント
- 脚を使って動く
- 近づいて介助する
- ねじらずステップ動作
- アイテム活用&環境整備
- 自分の体を大切に
「一人で頑張らない介護」を、今日から始めてみませんか?
あなたがの介護が少しでも安心・安全にできることを祈っています