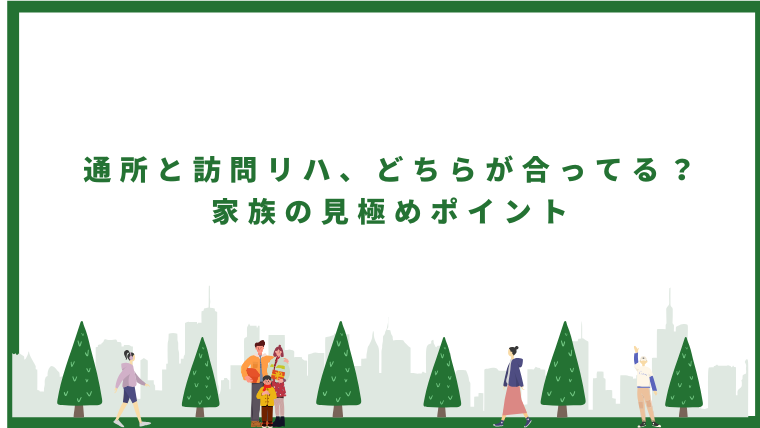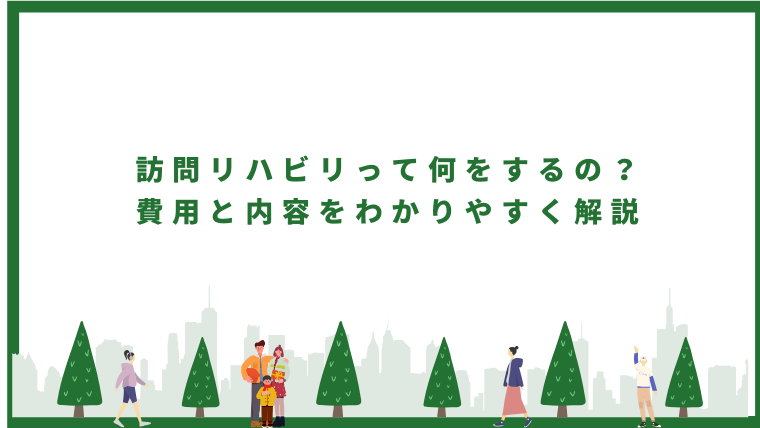ケアマネさんとの連携でリハビリが変わる!提案の仕方

はじめに:リハビリはチームで成り立っている
在宅介護の現場では、リハビリの成果がご本人の生活に大きく影響します
でも、そのリハビリがうまく進むかどうかは、実は「チーム連携」にかかっているんです
なかでも、介護支援専門員(ケアマネジャー)さんとの情報共有や提案の仕方によって、リハビリの内容や頻度、方向性が変わることも…
今回は、訪問看護ステーションに勤務する理学療法士として、ケアマネさんとよい連携を取るためのポイントと、リハビリをもっと効果的にするための「提案の仕方」について、わかりやすく解説していきます
ケアマネさんの役割とは?
ケアマネジャーさんは、利用者さんの生活全体を見守る“司令塔”のような存在です
介護保険サービスの調整やケアプランの作成だけでなく、リハビリや福祉用具の導入、医療とのつなぎ役も担っています
よくある誤解
- ケアマネさんは「リハビリのプロ」ではありません
- だからこそ、現場のリハビリ職(理学療法士・作業療法士)がわかりやすく情報提供する必要があります
連携がうまくいくとどうなる?
ケアマネさんとしっかり連携を取ることで…
- 必要なリハビリが必要なタイミングで導入される
- ご本人の希望がプランに反映されやすくなる
- 「生活の中での困りごと」がリハビリの目標になる
実際の例
Aさん(80代・女性)は、ベッドから立つのに時間がかかり、日々の生活に疲れきっていた様子でした
→ケアマネさんに「リハビリで立ち上がり練習をしたい」と提案
→結果、週1回の訪問リハが開始し生活の自立度が上がりました
ケアマネさんに伝わる「提案の仕方」とは?
ただ「リハビリがしたいです」では、伝わりません
以下のようなポイントを押さえると、伝わりやすくなります
① 現状と課題を明確に
「○○ができなくなってきている」「転びそうで危ない」など、状態とリスクを具体的にする
② リハビリの目的を共有する
「○○ができるようにするためにリハビリをしたいです」→生活とのつながりを意識すると説得力がアップ
③ 他職種との連携も意識
「看護師と連携して床ずれを予防したいです」など包括的に伝える
ご家族としてできること
リハビリ導入は、ケアマネさんだけに任せるのではなく、ご家族からの「こうしてほしい」も大切な情報源です
提案のコツ
- 「最近、歩きにくそうだけどリハビリで何かできることある?」と相談してみる
- 「トイレまでの移動が大変そう」など、生活の困りごとを共有する
在宅リハビリでよく使われる福祉用具も提案しよう

1. 手すり付き歩行器
おすすめ:島製作所のシンフォニーSP
室内でも屋外でも使いやすく、軽量設計で安全
歩くことに不安がある人はコチラの記事
→理学療法士が教える「歩く力」を保つ筋トレの基本
2. 座位安定のためのクッション
おすすめ:アウルケア【エクスジェル】
褥瘡予防や姿勢保持に最適です
長時間座るからこそクッション次第で大きな差があります
クッションに興味がある人はコチラの記事
→車椅子クッションで変わる!姿勢・褥瘡・快適さ
3. 自宅用段差スロープ
おすすめ:屋内用スロープ【モルテン】
ちょっとした段差の解消で転倒リスクを下げる
最近家でつまずくなぁと感じたらコチラの記事
→家の中の‘‘転倒ゾーン”を見直そう|場所別チェックリスト
→“最近よくつまずく…”は危険サイン?家族が気づくべき兆候とは
よくある質問(Q&A)

Q. どのタイミングでリハビリを相談すればいい?
A. 生活の変化を感じた時がチャンス
「最近、動きがにぶいな」「外に出たがらない」など、小さな変化もサインです
Q. ケアマネさんにどう伝えたらいい?
A. 難しく考えず、「困っていること」「心配なこと」をそのまま話してください
リハ職が同行している場合は、代弁も可能です
ケアマネさんに伝えるメモを作ってみよう
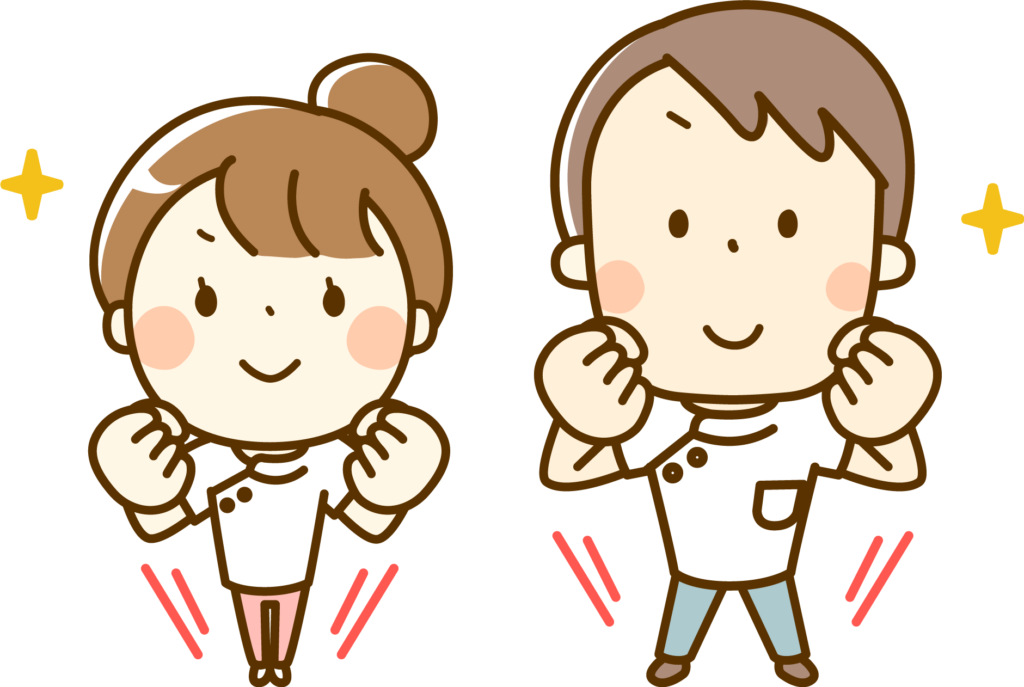
メモの例
- 〇日から歩きにくさが増えた
- トイレまで5分以上かかる
- 転倒が心配になってきた
- リハビリを導入したいと思っている
リハビリが「生活」に変わる瞬間
リハビリは、筋トレだけではありません
「自分でできることが増えた」「家族の負担が減った」
そんな“生活の質(QOL)”に直結する取り組みです
ケアマネさんときちんと連携して、チームで支えることで、その効果は何倍にもなります
おわりに:ケアマネさんも“仲間”です
理学療法士も、ご家族も、ケアマネさんも、全員が利用者さんの生活を支える仲間です
ぜひ遠慮せず、気になることがあれば積極的に伝えてみてください
そして、日々の生活が少しでも快適になるように、私たちリハ職も精一杯お手伝いします
関連記事のご案内