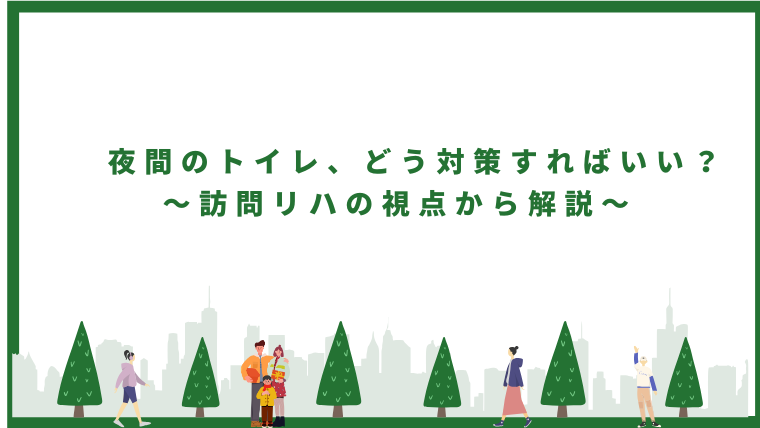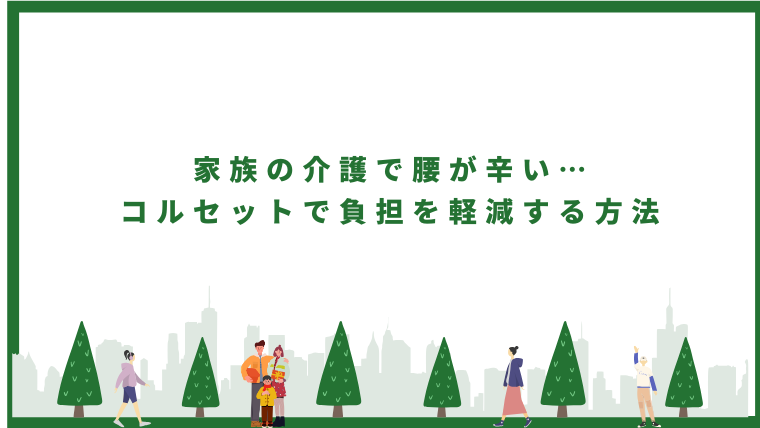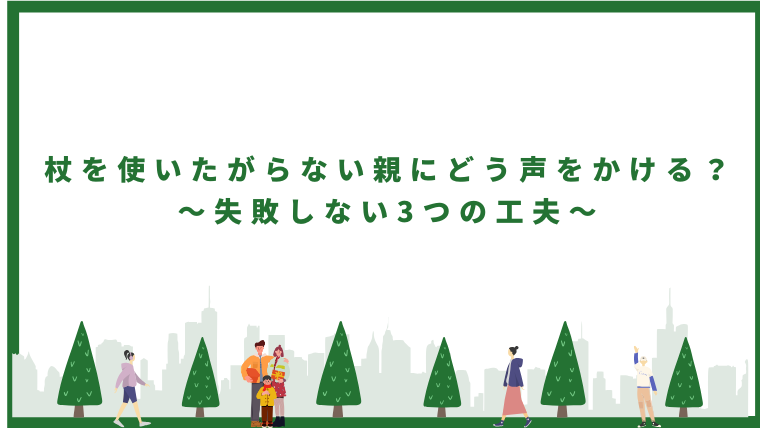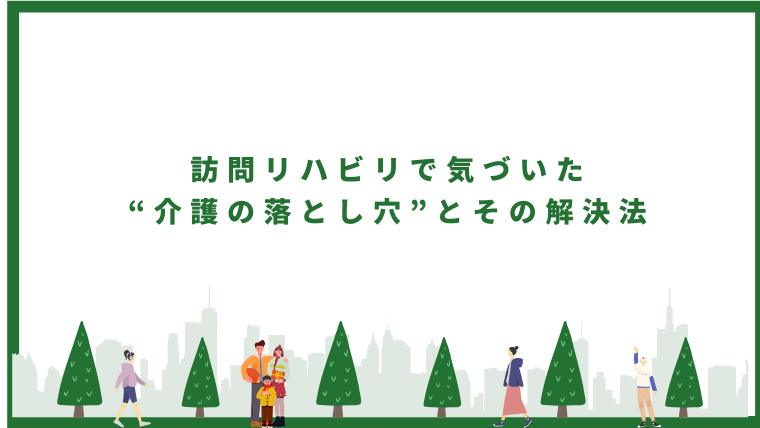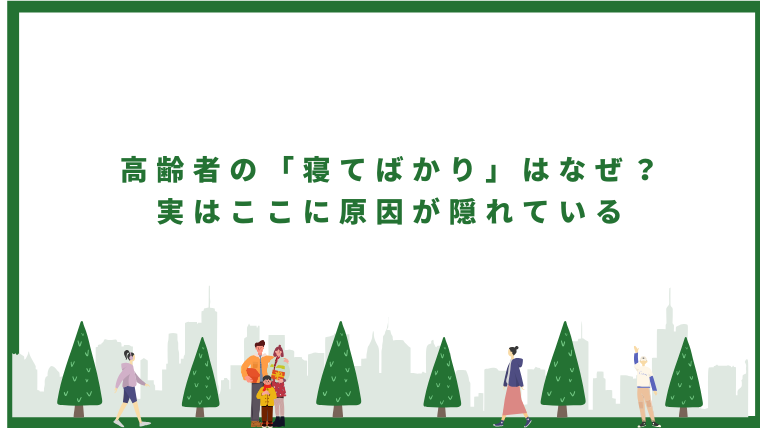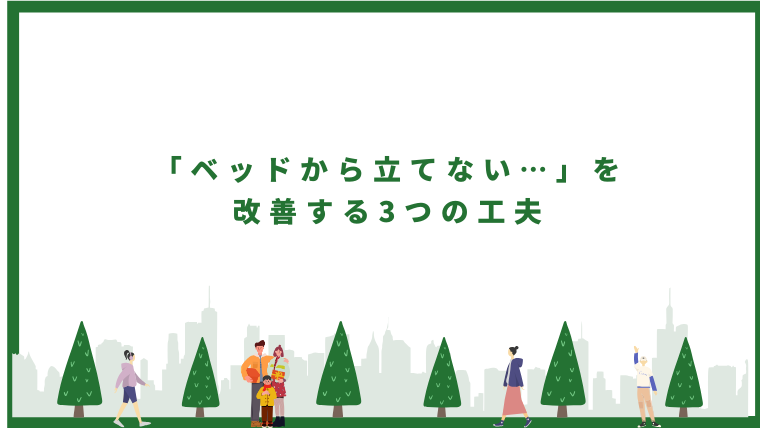“座っている時間が長い”のはなぜ危険?車いす・椅子生活の注意点と対策
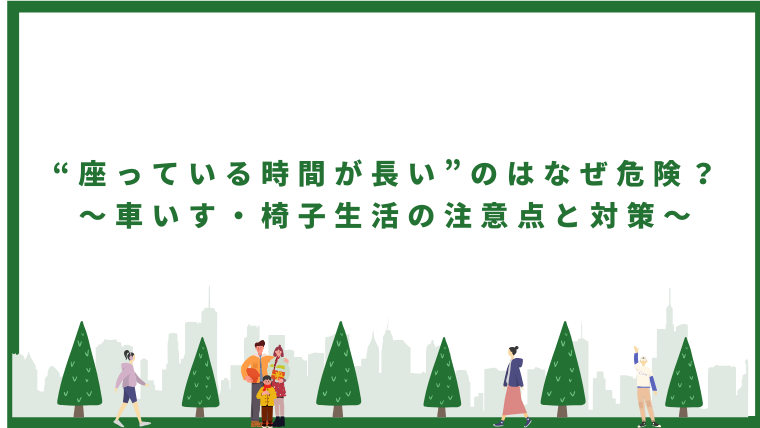
こんにちは。
在宅生活において、車いすや椅子での生活が中心となっている方は多くいらっしゃいます。しかし、「長時間座っている」という状態は、実は体にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
今回は、訪問看護ステーション勤務の理学療法士が座位生活のリスクとその対策について、現場での経験を交えながら解説します。
座りっぱなしがもたらす主なリスク

筋力の低下
座っている時間が長いと、下肢を中心とした筋力が低下しやすくなります。特に、太ももやお尻の筋肉(大腿四頭筋・大殿筋など)は、立ち上がりや歩行動作に重要な役割を果たしており、使わないことで急激に衰えてしまいます。
褥瘡(床ずれ)
長時間、同じ姿勢で座り続けると、骨が出っ張っている部分に圧力がかかり続け、血流が悪くなります。これが「褥瘡(じょくそう)」、いわゆる床ずれの原因となります。お尻・仙骨部・坐骨部などに多く見られます。
内臓機能・認知機能の低下
身体活動の減少は、腸の蠕動運動や心肺機能の低下を引き起こします。さらに、身体を動かす刺激が脳に伝わらなくなり、認知症リスクの増加も懸念されます。
深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)
下肢の血流が滞りやすくなり、血栓(血のかたまり)ができる可能性も。特に水分摂取量が少ない方や脱水傾向のある高齢者では注意が必要です。
座りっぱなしを防ぐ日常生活での工夫
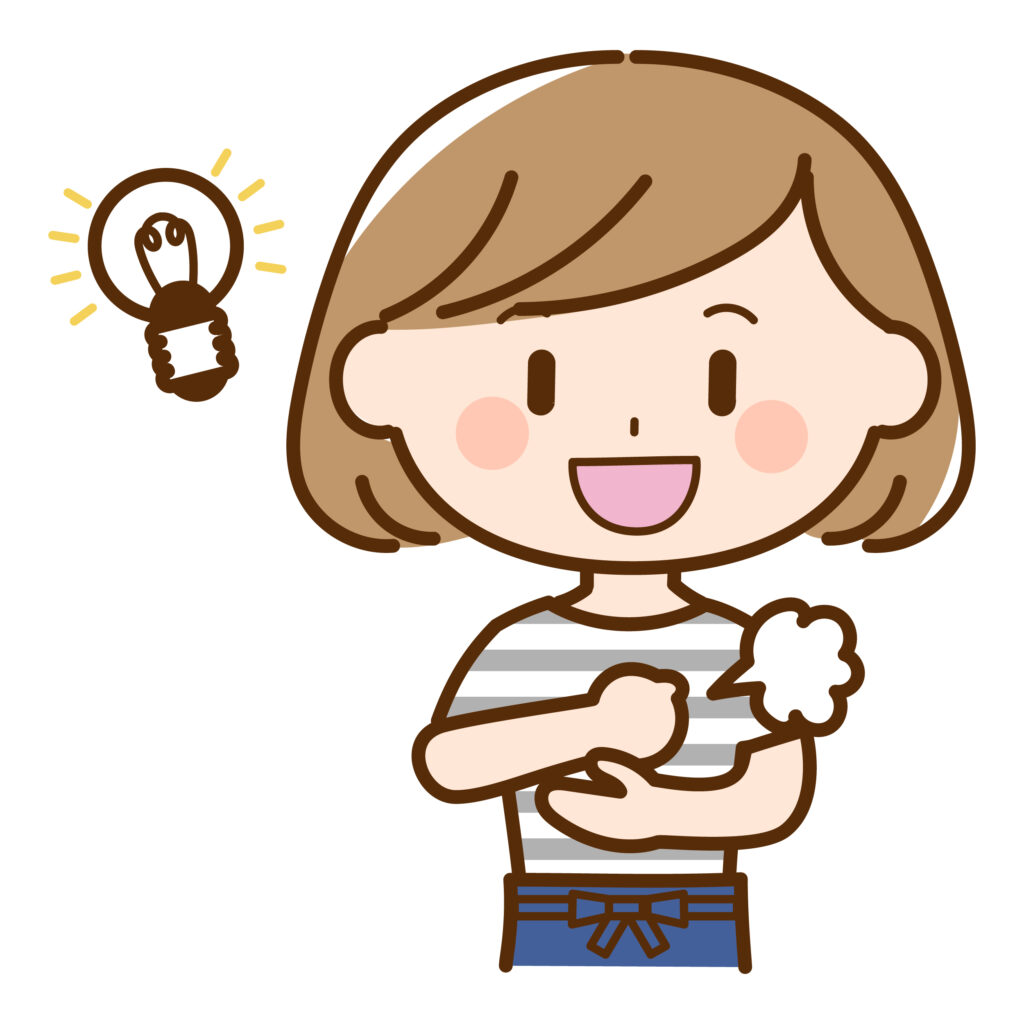
1時間に1回は姿勢を変える
「1時間ごとに5分動く」ことを目標にしましょう。可能であれば、立ち上がる、水を飲みに行く、窓辺まで移動するなど、軽い活動で構いません。
姿勢の調整をこまめに行う
背中が丸まりやすい方は、クッションを用いて骨盤を立てるサポートをしましょう。また、お尻が前にずり落ちる場合は、座面の後ろ側を前側より低くすることで防げます。
足裏がしっかり床につくようにする
椅子や車いすが高すぎると、足がぶら下がった状態になり、座位が安定しません。必要に応じて足台を使用し、足裏が床に接するように調整します。
足台がない場合は、雑誌などを重ねたものを足台にしてもいいと思います。
訪問リハビリでよく提案している簡単な対策
- 座面にバスタオルをたたんで傾斜をつけ、お尻の前滑りを防止
- 座ったままの足踏み運動や膝の曲げ伸ばしで、下肢筋力を維持
- ご家族がこまめに声をかけ、「動くきっかけ」をつくる
まとめ:動くことが予防になる
「座っているだけだから安心」と思われがちですが、動かないことで起きる問題は意外と多く存在します。
椅子や車いすでの生活でも、少しの工夫や意識で大きな違いが生まれます。ご本人もご家族も無理なく続けられる工夫を取り入れて、快適で安全な在宅生活を目指しましょう。